 建設業退職金共済制度 建設業退職金共済制度 |
 建退共制度のあらまし 建退共制度のあらまし |
|
この制度は、建設現場で働く人たちのために、中小企業退職金共済法という法律によって設けられた制度で、事業主が建設現場で働く労働者について、共済手帳に働いた日数に応じて共済証紙(掛金)を貼りその労働者が建設業界をやめたときに退職金を支払うという、いわば業界退職金制度です。
|
|
|
 民間の退職金共済とはここが違います。 民間の退職金共済とはここが違います。 |
|
1.安全確実かつ簡単
退職金は、国で定められた基準により計算して確実に支払われます。手続きはきわめて簡単です。
2.退職金は企業間を通算して計算
退職金は、A企業からB企業にかわっても、それぞれの期間が全部通算して計算されます。
3.掛金が一部免除
新たに加入した労働者(被共済者)については、掛金の一部(加入し初回交付の手帳の50日分)が免除されま す。
4.掛金は損金扱い
掛金は、税法上全額について、法人では損金、個人企業では必要経費として扱われます。(法人税法施行令代135条、所得税法施行令代64条第1項第1号及び第2項)
5.運営費は国が補助
運営に要する費用は、国の補助でまかなわれますので、納めた掛金は、運用利息を含めて退職金給付に充当されます。
|
|
|
 加入するには 加入するには |
|
各都道府県建設業協会内にある機構の支部で「共済契約申込書 」及び「共済手帳申込書 」及び「共済手帳申込書 」に必要事項を記入して申し込んでください。 」に必要事項を記入して申し込んでください。
加入の際は、労働者全員を加入させるようにしてください。共済契約が結ばれますと、機構から共済契約者証と各労働者に共済手帳が交付されます。 |
|
|
 加入すると 加入すると |
|
事業主には共済契約者証 労働者には共済手帳をお渡し致します。 |
|
|
|
| 共済契約者証 |
|
1冊目の手帳(掛金助成) |
|
2冊目以降の手帳 |
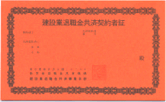 |
|
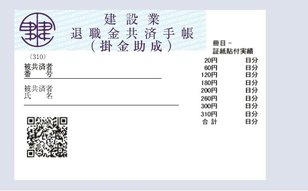 |
|
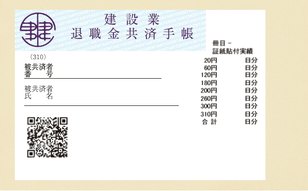 |
|
|
|
 契約できる事業主 契約できる事業主 |
|
建設業を営む方なら、専業・兼業を問わず、また許可を受けているといないとにかかわりなくすべて契約できます。 |
|
|
 加入できる労働者 加入できる労働者 |
|
建設業の現場で働く人たちなら、職種(大工・左官・とび・土工・電工・配管工・塗装工・現場事務など)にかかわりなく、また、日給・月給に関係なく加入できます。 |
|
|
 公共事業の受注に有利 公共事業の受注に有利 |
|
公共工事の入札に参加するための経営事項審査において、制度に加入し履行している場合には客観的・統一的評価の対象として加点評価されます。
また、公共工事発注機関では請負業者の指名に際し制度加入の有無をチェックし、さらに工事契約に際しては、掛金収納書を提出される措置をとっております。 |
|
|
|
|
 掛金を納入するには 掛金を納入するには |
|
共済手帳に証紙を貼付した時 |
|
|
|
|
共済証紙(1日券)310円 |
|
共済証紙(10日券)3,100円 |
|
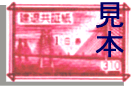 |
|
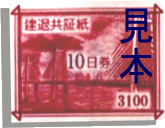 |
|
|
|
 共済証紙の購入は 共済証紙の購入は |
|
この制度は、公共・民間工事を問わず、すべてに適用となりますので、必要に応じて購入して下さい。
共済証紙は、最寄りの金融機関で共済契約者証を提示して購入して下さい。 |
|
|
 共済証紙の貼り方 共済証紙の貼り方 |
|
労働者に賃金を支払うつど(少なくとも月1回)、その労働者が働いた日数分の共済証紙を共済手帳に貼り、消印すれば掛金を納めたことになります。 |
|
|
 掛金が一部免除になります 掛金が一部免除になります |
|
新たな被共済者となった労働者については、掛金の一部が免除(掛金助成50日分)になります。
掛金助成欄にあたる日に働いた分は、証紙を貼付しないで消印のみにしてください。 |
|
|
 共済証紙の現物交付 共済証紙の現物交付 |
|
元請けが工事を請け負って、下請けにおろす場合、その工事に必要な共済証紙をまとめて購入し、その現物を下請けの延労働者数に応じて、末端の下請けまで交付するようにしてください。 |
|
|
 適用標識(シール)の掲示 適用標識(シール)の掲示 |
|
発注者から工事を受注した場合、現場事務所・工事現場の出入口等の見易い場所に、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」という標識を掲示してください。標識は機構の支部にあります。 |
|
|
|
|
適用標識(シール) |
|
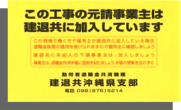 |
|
|
|
 退職金を受け取るには 退職金を受け取るには |
|
退職金は、共済手帳に貼り終わった共済証紙が24月(21日分を1ヶ月と換算)以上になって、建設関係の仕事をしなくなったときなどに労働者又はその遺族からの請求により、その請求人に直接支給されます。
退職金請求書に共済手帳を添えて機構の支部に提出してください。 |
|
|
|
|
退職金額早見表 |
|
| 年数(月数) |
退職金額(単位:円) |
|
年数(月数) |
退職金額(単位:円) |
| 1年( 12月) |
23,436 |
|
8年( 96月) |
721,308 |
| ( 18月) |
48,174 |
|
9年(108月) |
830,676 |
| ( 23月) |
76,167 |
|
10年(120月) |
945,903 |
| 2年( 24月) |
156,240 |
|
15年(180月) |
1,572,816 |
| 3年( 36月) |
234,360 |
|
20年(240月) |
2,256,366 |
| 4年( 48月) |
316,386 |
|
25年(300月) |
3,029,754 |
| 5年( 60月) |
410,781 |
|
30年(360月) |
3,902,745 |
| 6年( 72月) |
512,337 |
|
35年(420月) |
4,898,775 |
| 7年( 84月) |
613,893 |
|
40年(480月) |
6,036,723 |
|
|
(注) (1) この早見表は、最初から日額310円ではじめた人の場合で、証紙252日分を
1年と換算して計算した退職金の額です。
(2) 310円になる前から掛金を掛けている人の退職金は、それぞれの掛金日額に
応じて別に計算されます。 |
|
|
|
 退職金をもらうには 退職金をもらうには |
|
1.独立もしくは無職になって建設関係の仕事をやめたとき
2.建設関係以外の仕事に従事したとき
3.建設関係の事業所の社員や職員になったとき
4.けが又は病気になり建設関係の仕事ができなくなったとき
5.55才以上になったとき
6.死亡したとき |
|
|
 請求するには 請求するには |
|
退職金を請求するときは、「退職金請求書」に必要事項を記入して、共済手帳・住民票抄本(原本)を添えて支部へ提出してください。 |
|
|
 受取りは口座振込みで 受取りは口座振込みで |
|
退職金は「口座振込み」によって受け取れます。なお、口座がない場合はご相談ください。 |
|
|
 取り扱い金融機関 取り扱い金融機関 |
|
共済証紙の販売と退職金の支払いは、金融機関が組合の代理店となって行い、次の金融機関、全部本店及び支店の窓口」で取り扱っております。
なお、信用金庫と信用組合については、その全部が代理店となっているわけではありませんので、機構・支部にお問い合わせください。
都市銀行 地方銀行 信託銀行 日本債券信用銀行 商工組合中央金庫労働金庫 信用金庫 信用組合
(注)代理店となっていない信用金庫・信用組合及び農業協同組合では、退職金の口座振込みのみ取り扱っております。 |